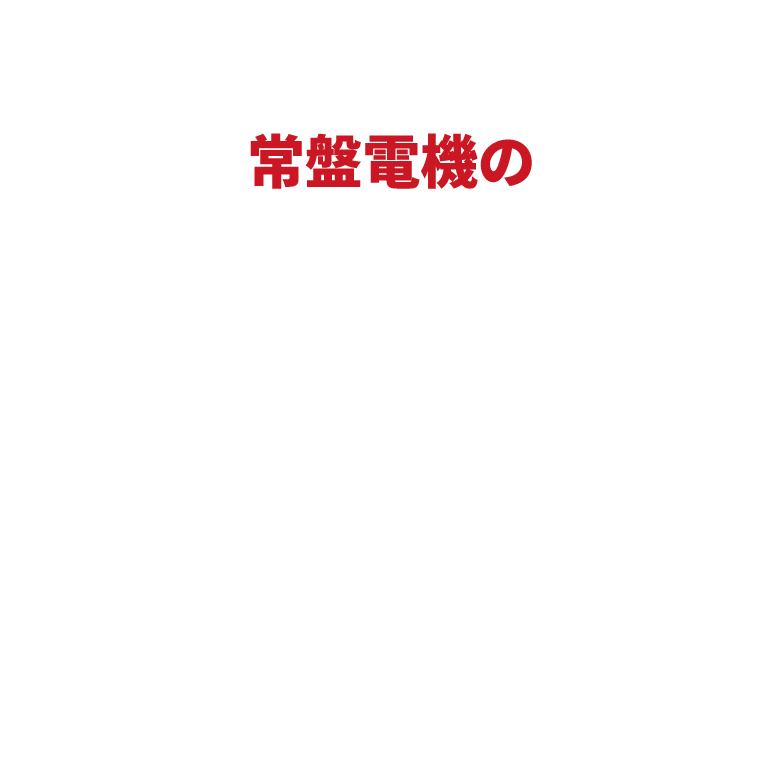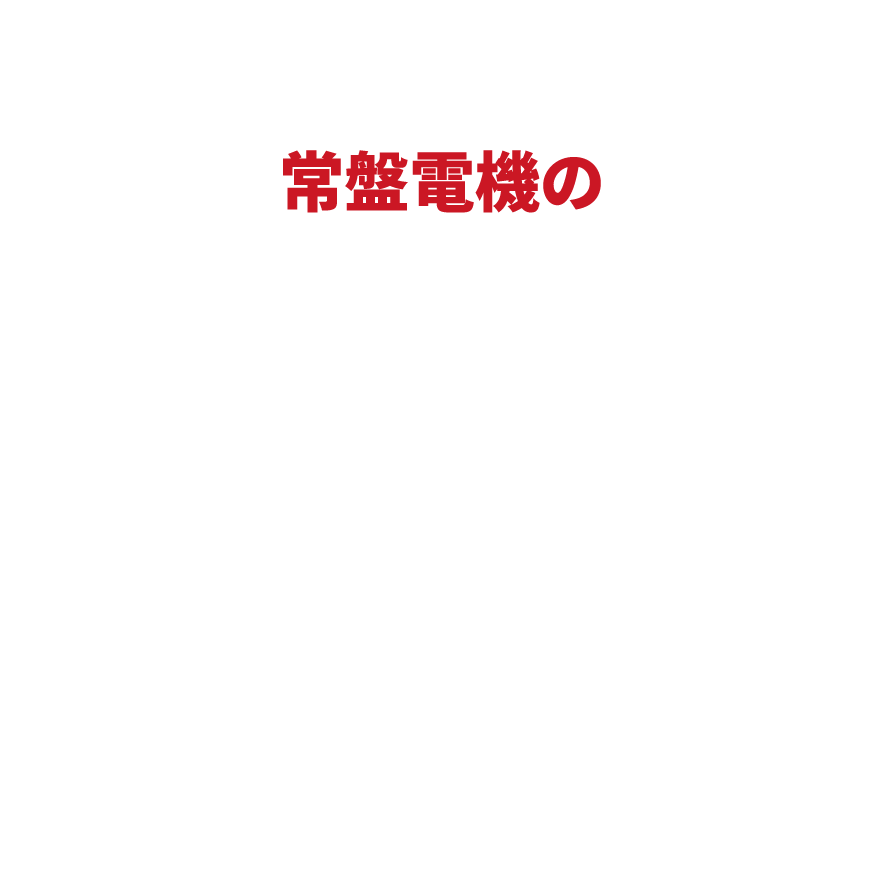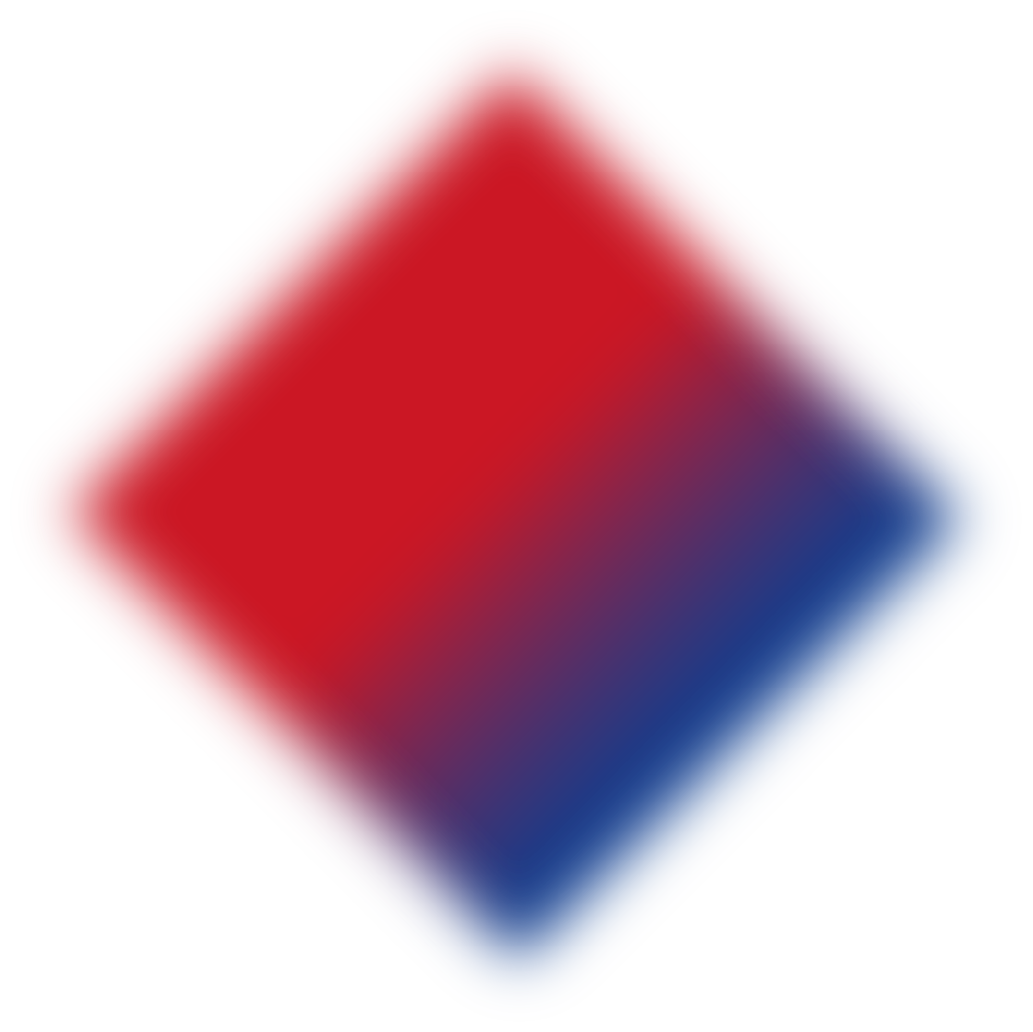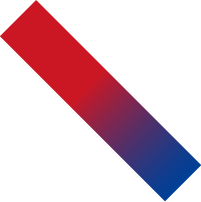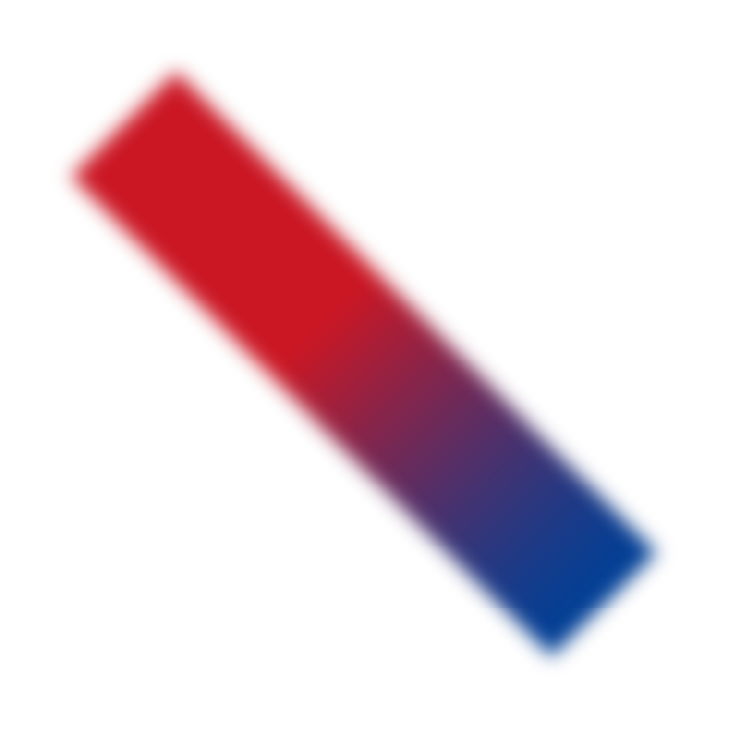それぞれのトップが語り合う
“当社の特徴と
未来の展望について“
執行役員
第1事業本部 本部長
山口 記生 さん

1996年に入社後、複数の部署で
マネージャーを務め、大阪営業所の責任者などを歴任。
2023年に執行役員および第1事業本部本部長に就任。
現在は、日立の産業機械や空調機器、HiKOKIの
電動工具などの販売・メンテナンスを担う部門の統括を担当している。
執行役員
第2事業本部 本部長
吉野 剛 さん

2004年入社。マネージャー、第2事業本部の
副本部長を経て、2016年に本部長に就任。
FAシステムや協働ロボットなどの新規商材の新規事業の拡大に尽力する。
2023年には執行役員に就任。
現在はソリューション部門全体の統括をする。
製造業を取り巻く環境の変化と未来への挑戦




次世代に向けたビジョンと成長戦略




次世代の人材に求めるものとは?
次世代の人材に求めるものとは?

 常盤電機株式会社
常盤電機株式会社